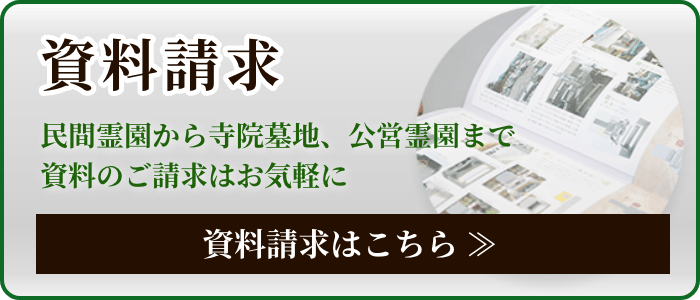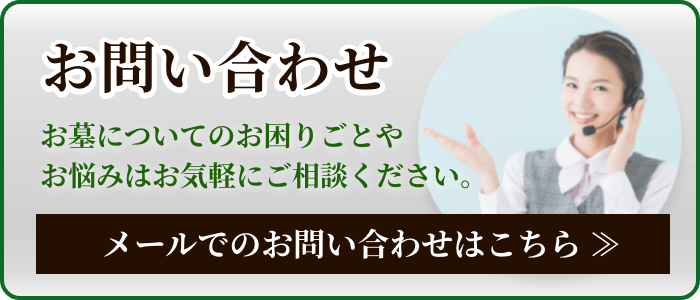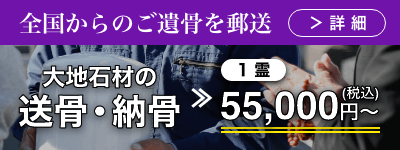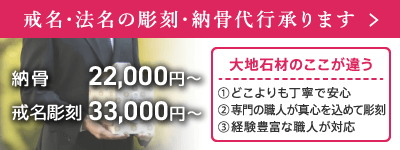墓じまいをしたいけど、「お布施はいくら包めば良いの?」「マナーは大丈夫かな?」と不安ではありませんか?本記事では、お布施の相場金額から正しいマナー、さらに離檀料など気になるポイントを徹底解説します。この記事を読めば、墓じまいのお布施に関する不安が解消され、安心してスムーズに進められるようになります。ぜひ最後までお読みください。
目次
墓じまいのお布施とは?必要になるタイミングと意味
墓じまいとは、お墓を撤去する前にお墓の魂抜きを行う儀式(閉眼供養)をすることです。この際、僧侶に読経してもらうため、お布施をお渡しします。つまり「墓じまい=閉眼供養(=お布施)+墓石撤去の手続き」という構成になります。
お布施は僧侶への読経の対価ではなく、あくまで感謝の気持ちのお礼として渡すものです。そのため「お気持ちで結構です」と言われることが多く、金額に明確な決まりがない背景があります。
お布施が必要になる主な場面は以下の通りです:
- 閉眼供養:現在のお墓で魂抜きをする儀式(ほぼ必ず行う)
- 開眼供養:新しいお墓で魂入れをする儀式(新墓を建てる場合のみ)
- 離檀:寺を離れる際のお礼(檀家の場合のみ)
これらの場面でお布施または謝礼が発生することを理解しておくと、費用の見通しが立てやすくなります。
墓じまいのお布施の相場はいくら?金額の目安と幅がある理由
一般的には3万円〜10万円程度が相場です。
ただし金額に幅があるのは、以下の理由によるものです:
- 地域や寺院により相場が異なる:都市部の格式高い寺院では高め、地方では比較的安めなど差があります
- お寺との付き合いの長さ:先祖代々で関係が深いほど多め(上限近くの10万円前後)を包むケースがある
- 僧侶手配方法:菩提寺に頼む場合と、インターネット経由で初めての僧侶にお願いする場合で金額に違いがあり、後者は3〜5万円程度と低め
ケース別のお布施額の目安
| ケース | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 付き合いのあるお寺に依頼 | 3〜10万円 | 先祖代々なら10万円程度包むことも |
| ネット等で初めて依頼する僧侶 | 3〜5万円 | サービスごとに定額料金の場合も |
その他のお布施
新しいお墓で開眼供養をする際は別途3〜5万円程度のお布施を用意します。永代供養墓や樹木葬での納骨式でも同程度を目安にしましょう。
離檀料について
離檀料は厳密にはお布施と別物ですが、墓じまいに伴い発生しやすい費用です。相場は5万〜20万円と幅があります。必要な場合とそうでない場合があるので、お寺に確認しましょう。負担が大きい場合は住職と相談することをおすすめします。
墓じまいのお布施の正しいマナー|封筒の選び方・書き方・お札の包み方
お布施を包む封筒(不祝儀袋)は何を使う?
白無地の不祝儀袋が基本で、水引は通常不要ですが地域差があります。奉書紙を使った丁寧な包み方もありますが、「御布施」と書かれた既製封筒でも問題ありません。コンビニや100円ショップでも購入できます。
お布施の表書き・中袋の書き方
- 表書き:濃い墨で「御布施」と中央に書きます(薄墨は使いません)
- 施主名:表書きの下に施主の名前を書きます
- 中袋:住所・氏名・金額(旧字体で)を書きます
- 御車代・御膳料:別袋にしてそれぞれ表書きします
お札の向きと入れ方
- 新札・旧札どちらでも構いません(香典とは違い新札でも失礼に当たりません)
- お札は人物の肖像が表面上側になるように揃えます
- 汚れたお札は避けましょう
袱紗の使い方
金封は必ず袱紗に包んで持参します。僧侶に渡す直前に袱紗から取り出すのが正しいマナーです。
僧侶へのお布施の渡し方・タイミング|当日のマナー総まとめ
お布施を渡すタイミング
一般には法要が始まる前(読経前の挨拶時)か、法要後に僧侶がお帰りになる前にお渡しします。
- 開始前の場合:僧侶がお見えになったタイミングで「本日はよろしくお願いいたします」と挨拶しながらお渡しします
- 終了後の場合:読経・お勤めが終わり法話等が一段落したら「本日はありがとうございました」と感謝を伝えお渡しします
お布施の渡し方
- 袱紗から金封を取り出します
- 切手盆やお盆があればその上に載せて向きを正して差し出します
- 僧侶が受け取ったら盆を下げます
当日の服装と持ち物
服装:基本は喪服(略礼服)を着用。作業のみ立ち会う場合も派手な服装は避け、落ち着いた服装で
持ち物チェックリスト:
- お布施(封筒に入れ袱紗に包む)
- 改葬許可証
- 数珠
- 手土産(菓子折り等、任意)
- お供え用線香・花(任意)
一言アドバイス:僧侶も慣れているので多少ぎこちなくても大丈夫です。気持ちよく感謝を伝えることが一番です。
お布施以外で準備が必要なお金|御車代・御膳料・離檀料
墓じまいでは状況によってはお布施以外にもお金を包む場面があります。それが御車代・御膳料、そして離檀料です。
- 御車代:僧侶の交通費として渡すお金。相場5千〜1万円。遠方から来てもらう場合のみで、寺院が同じ敷地内なら不要。お布施と別封で「御車代」と表書きし渡す
- 御膳料:僧侶が会食に出席しない場合の食事代お礼。相場5千〜1万円。閉眼供養では会食を設けないことも多いので、発生するのは稀。これも別封筒に「御膳料」と書いて渡す
- 離檀料:檀家を離れる際に寺院に渡す謝礼。相場5万〜20万円と幅広い。お寺によって不要の場合もあるので事前確認必須。必要な場合は閉眼供養時か離檀の挨拶時にお渡しする
※御車代・御膳料はあくまでお布施に追加で発生する可能性がある費用です。全て必ずかかるわけではありませんが、心づもりしておきましょう。
墓じまいの流れとお布施を渡すタイミング【ステップ別解説】
- 親族と寺に相談:墓じまいの意向を関係者に伝え、了承・協力を得る
- 改葬許可証の取得:自治体で改葬の許可証を発行してもらう(寺院の署名が必要)
- 閉眼供養(魂抜き法要):僧侶にお経をあげてもらい遺骨を取り出す儀式。当日ここでお布施を渡す
- 墓石の解体撤去:石材店が墓石を撤去し更地にする
- 墓地の返還と離檀:墓地管理者に区画を返還し、菩提寺を離れる挨拶をする(離檀料を渡す場合あり)
- 新しい供養先で納骨:遺骨を新たな墓所や納骨堂に納め、開眼供養/納骨式のお布施を渡す(必要な場合)
※閉眼供養はほぼ必須ステップで、お布施をお渡しする場面になります。親戚への体裁や石材店の都合からも、省略せず行うことをおすすめします。
墓じまいのお布施に関するよくある質問(FAQ)
Q:墓じまいで石材店の作業員さんに心付けは渡すべき?
A:基本的には不要です。工事代金に含まれているため、石材店への個別の謝礼は不要です。ただ、特別にお世話になったと感じた場合や地域の慣習で決まっている場合は、任意で数千円程度の心付けを渡すこともあります。
Q:離檀料は必ず払う?どう決めればいい?
A:寺院によって対応が異なります。請求しないお寺もありますし、請求がある場合でも金額は「お気持ち」でと案内されることが多いです。絶対に支払わねばならない決まりはありません。もし提示された額に納得できない場合は、住職に相談してみるのも一つの方法です。
Q:墓じまいに親族として呼ばれました。香典やお布施は持参すべき?
A:参列者がお布施や香典を用意する必要は基本ありません。墓じまい(閉眼供養)は葬儀や法事とは異なり、参列者から香典を頂く習慣はありません。ただ、気になるようであればお花やお供え物を持参する程度で十分でしょう。
Q:僧侶に「お気持ちで」と言われるといくら包めば良いか余計わかりません…
A:悩ましいところですが、一般的な相場は3万〜10万円です。迷う場合はお寺の世話役や親族に率直に相談してみましょう。「皆さんはどのくらい包んでいますか?」と尋ねれば、目安を教えてもらえることが多いです。無理のない範囲で、真心を込めて包めば問題ありません。
Q:永代供養墓に改葬する場合、新しいお墓へのお布施も必要?
A:はい、必要です。墓じまい後、永代供養墓や納骨堂など新しい供養先で納骨法要を行う際にもお布施をお渡しするのが一般的です。相場は3~5万円程度で、宗派や供養先によって異なります。事前に受け入れ先に確認し、必要なら忘れず準備しましょう。
まとめ|墓じまいのお布施準備はこれで安心!
- 墓じまい時の閉眼供養ではお布施(3〜10万円程度)が必要。感謝の気持ちとしてお寺にお渡しするお金
- お布施は不祝儀袋に「御布施」と書き、僧侶に渡すタイミングは法要の前後が一般的。袱紗やお盆を使って丁寧に手渡す
- 御車代・御膳料は状況に応じて用意し、離檀料は寺院と相談の上で包む。必ずしも高額を払う必要はなく、気持ちが大事
- 墓じまい全体の流れを把握し、早めに準備すればスムーズ。不安な点は専門家に相談するなど、無理なく進めましょう
墓じまいは人生の大きな節目ですが、適切な準備とマナーで進めればきっと円満に完了できます。本記事のガイドを参考に、不安を一つ一つ解消していただければ幸いです。