01 型紙を作る

お客様からいただいた原稿を元に、ゴムシートを切り抜いて型紙にします。美しく刻むための最重要工程となるため、一文字ずつ丁寧に心を込めて作成します。
市原市営能満霊園・市原市営海保霊園・長南町営笠森霊園の納骨・追加彫刻はお任せください

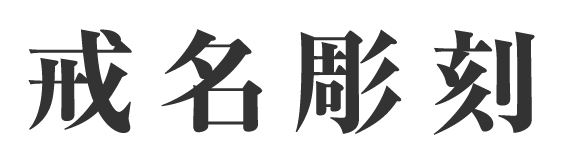
こんなお悩みの方に
墓石に戒名を刻むのは、故人が安心して極楽浄土へ行けるようにするためです。
故人の遺骨が眠っている墓石に戒名をもらって彫刻することで、先祖に成仏してもらおうという意味合いがあります。
大地石材では、年間150件以上の実績がありますので、初めて戒名彫刻をお考えの方は
実績と信頼の大地石材にお任せください。
戒名彫刻料金:
38,000円〜(1霊分)
※戒名(法名)、没年月日、俗名、年齢
戒名彫刻に必要なもの

お客様からいただいた原稿を元に、ゴムシートを切り抜いて型紙にします。美しく刻むための最重要工程となるため、一文字ずつ丁寧に心を込めて作成します。

彫刻する部分に、型紙を丁寧に貼り付けます。曲がったり歪んだりしないよう、ミリ単位で位置を調整しながら位置を決めていきます。

彫刻をする箇所以外の周辺の墓石を傷つけないよう、しっかりと養生をします。墓石の材質によっては傷がつきやすいものもあるので、注意して対応いたしますのでご安心ください。

砂を吹き付けて彫り込んでいきます。粉砂が飛ばないように、囲いをして作業していきます。なお墓石が黒い場合は、文字がくっきりと浮かび上がるよう、彫り込み後に白または黒のペンキを入れていきます。

仕上がりを目視で丁寧に確認します。細かな欠けやムラが無いか、清掃や補修を施して仕上げます。

最終確認後、施工完了です。ご依頼内容に応じてお写真のご送付やご報告も対応いたします。

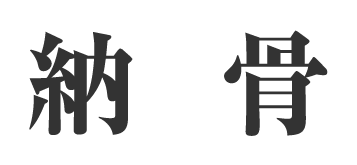
納骨費用:22,000円〜
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
ご納骨には必要書類の提出や塔婆の手配・墓碑への追加彫刻など、さまざまな準備が必要になってまいります。お寺さま・霊園管理者・石材店とそれぞれにお打ち合わせが必要になるため、以下の流れをご参考にしてみてください。
ご納骨を執り行う時期に特に決まりや法律があるわけではありませんが、一般的には四十九日の忌明けを迎えてそのまま納骨式を行うことが多いです。最近ではご葬儀の後や火葬当日に行う方もいらっしゃいます。
お骨壺をお持ちでない場合は、ご納骨までご自宅に安置するか、一時預かりが可能な納骨堂に預かっていただくケースが多いです。その場合には、一周忌法要と合わせてご納骨式を執り行うことが多くなります。

四十九日法要と合わせて納骨をする場合、その日程をお寺さまに相談して決めます。僧侶に読経を依頼する場合は僧侶の予定も確認しておくことも必要です。また霊園の手配も必要です。
納骨式の前までに、墓碑や板石へ故人の名前を彫ってもらう必要があるので、石材店へ依頼書をご用意ください。混み合う時期によっては数週間〜数ヶ月前からのご依頼が安心です。

納骨の際には「埋葬許可証」が必要です。これは死亡届と交換にもとづき住まいの市町村で受け取ることができる火葬許可証に、火葬場で捺印してもらったものになります。霊園は法律によりこの埋葬許可証を保管する必要があるため、納骨時の際には必ず霊園墓地の管理者に提出してください。
墓地使用許可証は、霊園側から発行される証明書です。「永代使用承諾書」などと霊園によって呼び名が違う場合もあります。工事を行う時や御納骨の際に確実にその墓地を契約した者が墓を建立しているのだと霊園側に証明できるよう、墓地使用許可証が必要になります。
霊園によっては永代使用料が記載された永代使用承諾書(永代使用承認証など、名称が違うこともあります)の提出を求められる場合があります。永代使用承諾書は墓地を生涯にわたって使用する際に霊園から発行されているものです。
共同墓地などの場合、上記以外の書類を求められることもありますので、管理している役員やお寺さまにご確認ください。
納骨式の時間は20〜30分程度となることがほとんどです。時間帯は一般的に11〜16時ごろに行われるケースが多くなっています。
埋葬許可証など、霊園側に提出する書類一式をお持ちください。
だいたい3,000〜5,000円程度のものをご用意いただくことが多いです。お花屋さんにご相談いただくと適宜見繕ってくれます。
お菓子や果物が一般的です。故人が好きだったものをご用意ください。納骨後はお持ち帰りいただく場合があります。
納骨式にあたって必要になります。地域や宗派により持ち物が異なることがあるため、お寺さまにご確認ください。
お寺さまにご手配いただく必要があります。
お寺さまへ読経への謝礼として準備が必要です。相場は3〜5万円ほどになります。
霊園の場合、管理事務所に埋葬許可証などの必要書類を提出して手続きを行う必要があります。
お寺さまの指示で納骨式を執り行います。お寺さまのやり方によりますが、一般的には遺族代表の挨拶から始まり、お坊さんの読経・参列者の焼香という流れになります。
代表の方に確認していただいた後、蓋を閉めさせていただきます。ご納骨した後は、雨水が入り込まないよう目地を塞ぎます(当日その場で塞げない場合は、後日改めてお伺いすることもございます)。
納骨をスムーズに執り行うためには、事前の準備が必要になります。今回ご紹介した納骨に必要な書類や準備をしっかりと行いましょう。なお、宗教や宗派によって異なるので、お寺さまに事前にご確認しておきましょう。