お墓の購入は一生に一度のことですが、よくわからないという人は多いのではないでしょうか。
お墓の購入金額の内訳や、何が理由で金額が高くなったり安くなったりするのか理解できれば不安も解消されると思います。
この記事では、どうすればお墓を安く購入することができるのか、その内訳やポイントについてお伝えします。
安いお墓はいくらで買えるのか?

安いお墓はいくらくらいで買えるのでしょうか。お墓の消費者全国実態調査(2021年)によると、一般墓の平均購入価格は169.0万円です。
また、購入されている人は100万円前後が最も多いようです。その内訳やどうすれば安い金額で購入できるか、詳しく見ていきましょう。
お墓にかかる費用と内訳
お墓を建てるときの費用の内訳大きく分けると、墓石代、墓地代、管理費代に分かれます。それぞれみていきましょう。
墓石代
石質(硬さ・色・石目)や産出地、採掘量によって石の性質や価格には大きな幅があります。墓石の加工にもオリジナルな細工、手の込んだ細かい加工の多いデザインは手間がかかるため加工賃が上乗せされることも多いです。
工事に関して、立地的に施工や運搬がしにくい霊園・墓地(区画)は費用が加算されることがありますので、きちんと見積もりを取ってもらいましょう。
墓地代
永代使用料ともいわれることがあります。墓地代の価格は住宅の不動産と同じように、立地やアクセスが良いところ、土地としての希少価値が高く人気がある地域ほど、高くなります。
永代使用料はお墓を継ぐ人がいなければ立てたお墓を維持できないということを意味しますので、お墓を立てるときには誰が継承していくかを考えておきましょう。
管理費
使用する区画によって管理費の料金が規定されており、管理運営主に定期的に支払う義務があります。公営霊園、民営霊園、寺院墓地の3つに分類されていて、それぞれ管理費は異なりますので注意が必要です。
公営霊園は自治体が運営しているため、比較的金額が安くなる傾向があるので、安いお墓を探している人は一度調べてみる良いでしょう。
お墓を安く建てるためのポイント

お墓を安く建てるためのポイントは3つあります。
お墓を建てる場所の立地
周辺環境が良く、設備が整っているレベルの高い施設は墓地代が高い傾向があります。特にアクセスの良い都心の霊園は、金額が高くなりがちです。
墓地代を安く済ませたい場合は、なるべく都心にお墓を建てることは避けましょう。
区画の大きさを小さくする
墓石を置く区画の大きさが大きければ大きいほど金額が高くなります。そのため安い金額で済ませたい場合は、サイズは最小限に抑えた区画にするようにしましょう。
同じ霊園であっても区画が違うだけで、何十万円も金額が違う場合もありますので注意してください。
墓石に使う石材を安いものにする
国産の石で50種類、外国産の石で100種類以上あるといわれています。日本で採れる石の種類であっても安い石材はありますが、基本的には外国産の石材の方が安い場合がほとんどです。
なるべく小さめのサイズでシンプルなデザインの墓石を選びましょう。
お墓を安さだけで考えるとリスクもあり
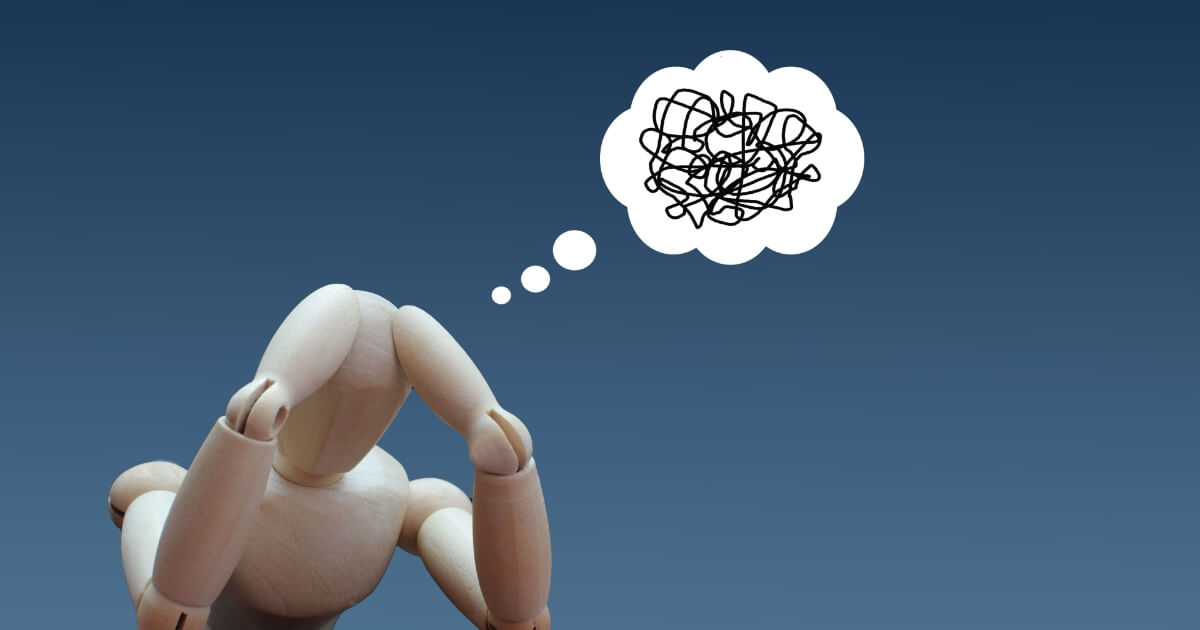
費用の安いお墓にはそれなりのリスクがあります。例えば、費用がが安いお墓としては、合祀墓が挙げられます。
合祀墓は複数の遺骨を1ヶ所にまとめて供養するのが特徴ですが、お骨を取り出せないことがあるのです。
一旦合祀墓に埋葬すると、後からお骨を取り出し個別に供養したいと申し出てもそれが叶いこともありますので、確認しましょう。
まとめ
どうすればお墓を安く購入することができるのか、その内訳やポイントについてお伝えしました。お墓を建てるときの費用の内訳大きく分けると、墓石代、墓地代、管理費代に分かれます。
立地や墓石の種類、管理を運営している場所によってそれぞれ費用が異なりますので、ご親族とぜひ相談してみてください。














