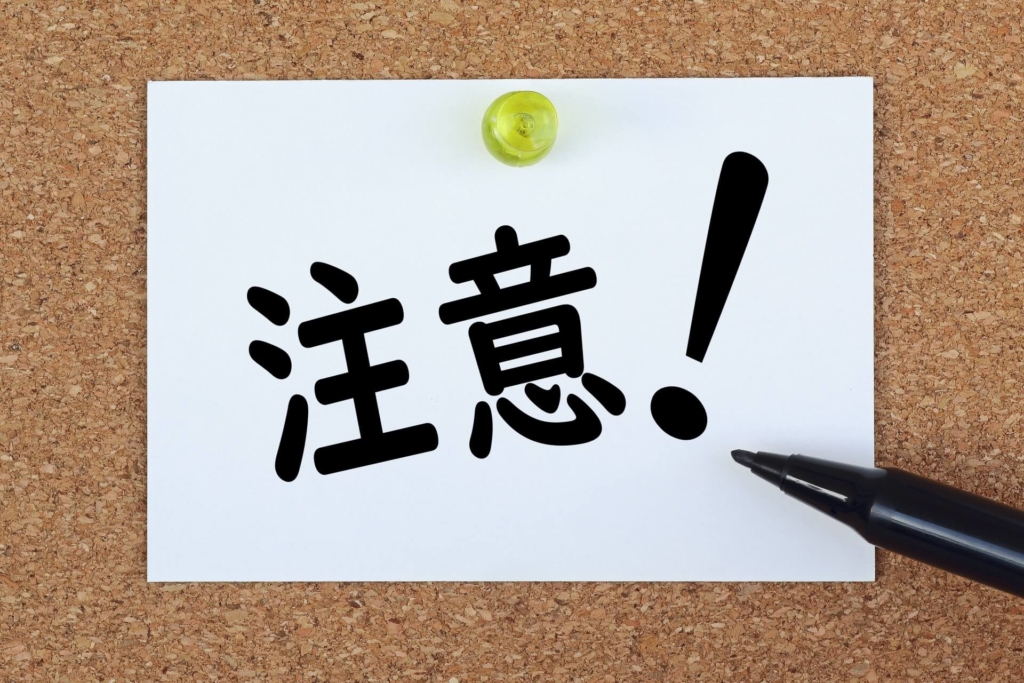お墓参りに行くとまわりに雑草が生えていてうんざりしてしまう、ということもあるでしょう。雑草は抜いてもすぐに生えてくることも多いものです。
こまめに手入れができればよいのですが、お墓が遠い場所にあるなどの理由で頻繁に手入れができないこともあるかもしれません。
今回は、お墓に生える雑草対策について雑草の種類や効果的な方法など、簡単にできる雑草対策についてお伝えします。
簡単にできる雑草対策
まず簡単にできる方法としては、玉砂利などの敷石を敷くことです。敷石を敷き詰めてしまえば雑草が生えにくくなります。
敷石は色や種類もさまざまで、白や黒、青みがかった色などがあります。手軽にできる方法というだけではなく、お墓のイメージを変えることもできます。
ただ、敷石だけでは強い雑草などは隙間から生えてくることもあります。そのような雑草などには除草剤も効果的です。効果も持続するのでお墓にあまり頻繁に行けない場合にも適しています。
除草剤には雑草の種類を選ばない非選択性除草剤と、種類によって使い分ける選択性除草剤があります。また、薬剤がかかった部分だけ枯れる即効性があるタイプと、雑草の成長を妨げ半年以上効果が持続するタイプがあります。
他にも防草シートや固まる土などといった方法があります。雑草が生えてこないようにするにはコンクリートにしてしまうのも一つの方法です。
雑草を取り除く方法の選び方

土の中に茎を伸ばす性質があるスギナやドクダミなどは、目に見えている部分だけ排除してもすぐに生えてきてしまいます。また、セイダカアワダチソウやカヤなど多年生の雑草は、枯れたように見えても毎年生えてきます。
生命力の強い雑草に対しては、コンクリートが効果的と言われていますが、墓地や霊園によっては許可が下りない場合があります。またコンクリートは除草剤や玉砂利などの敷石よりも費用がかかります。
除草剤は手で雑草を取り除くよりも楽な方法ですが、種類を選ばないと効果が出なかったり、また効果がありすぎると周りの植物や墓石にまで影響を与えたりするリスクもあります。
このようなデメリットを考えると、敷石を敷く方法が安全で見た目もキレイです。敷石の下に防草シートを敷くとより効果が期待できるでしょう。
雑草対策の注意点
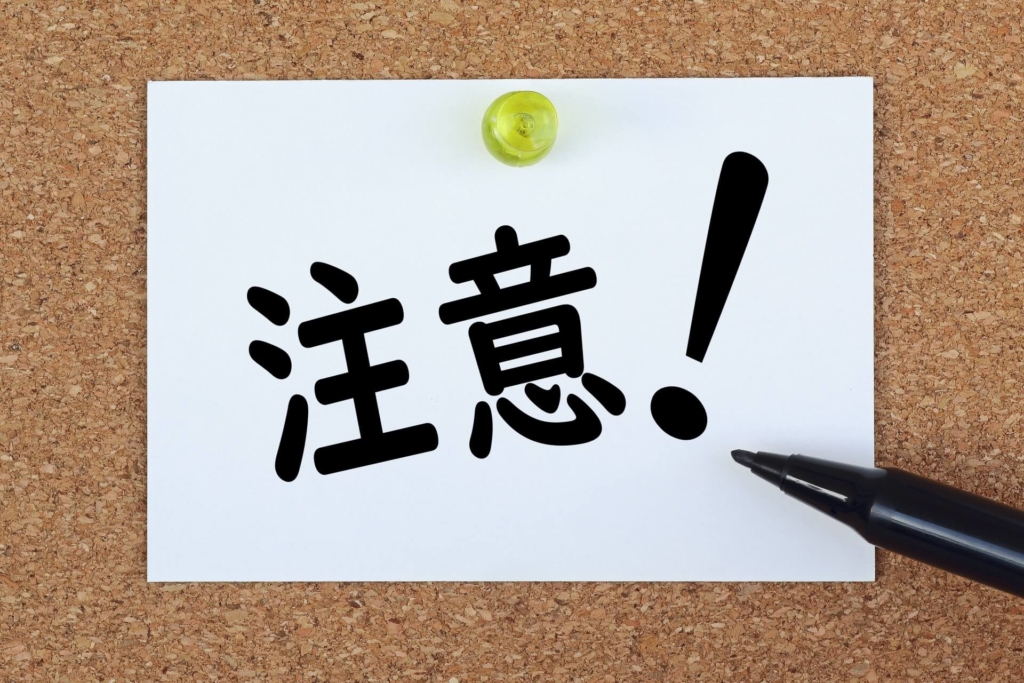
雑草対策をしようとしても、墓地や霊園によって許可が出ない方法もあります。特に除草剤などは周りに影響を与える危険もあるため禁止となっていることもあるので注意が必要です。
また、塩をまく方法もありますが、大量にまきすぎると墓石にも影響を及ぼすこともありえます。雑草対策は墓地を管理している霊園やお寺さんに事前に相談して、適切な方法で行うようにしましょう。
なお、霊園やお寺さんに相談する前に、まずはお付き合いのある石材店に相談する方が間違いがありません。お客様と霊園などの間に入って話を通してくれたり、専門家の視点からより良い提案をしてくれるはずです。
まとめ
お墓の雑草対策としては、除草剤や玉砂利、防草シート、コンクリートなどさまざまな方法があります。しかし、雑草には種類があり適した方法でなければ効き目が期待できないこともあります。
また、霊園や墓地によっては許可が下りない場合もあります。雑草の種類や生えてくる時期、墓地や霊園に迷惑をかけない方法などを確認し、適切な方法を選択しましょう。