近年ライフスタイルの変化により、従来のお墓ではなく納骨堂に遺骨を収蔵する人が増えています。また、これから納骨堂の利用を検討している人も多いことでしょう。
そこで今回は、納骨堂の特徴や種類、費用相場やメリット・デメリットについて解説します。この記事をとおして、納骨堂についての理解が深まれば幸いです。
納骨堂とは?特徴や種類を解説
納骨堂とは、遺骨を収蔵するスペースを備えた建物のことです。お墓と異なり、継承を前提としないで期間を定めて利用します。個人で納骨することもできれば、夫婦など家族単位での納骨も可能です。
納骨堂には、「棚型」・「ロッカー型」・「仏壇型」・「墓石型」、と納骨方式によって種類が分かれています。
棚型やロッカー型は値段が安くコンパクトに納骨できるのが特徴です。仏壇型や墓石型は納骨スペースと仏壇・墓石がセットになっていて、その場で礼拝が可能です。
また、収蔵スペースに、また運営主体も「民間」・「公営」・「寺院」によって分かれています。民間・公営の運営は宗派による制限はなく、寺院の運営のほとんども利用時に檀家になる必要はありません。宗派関係なく利用できるのも納骨堂の特徴です。
納骨堂が増えている理由とは
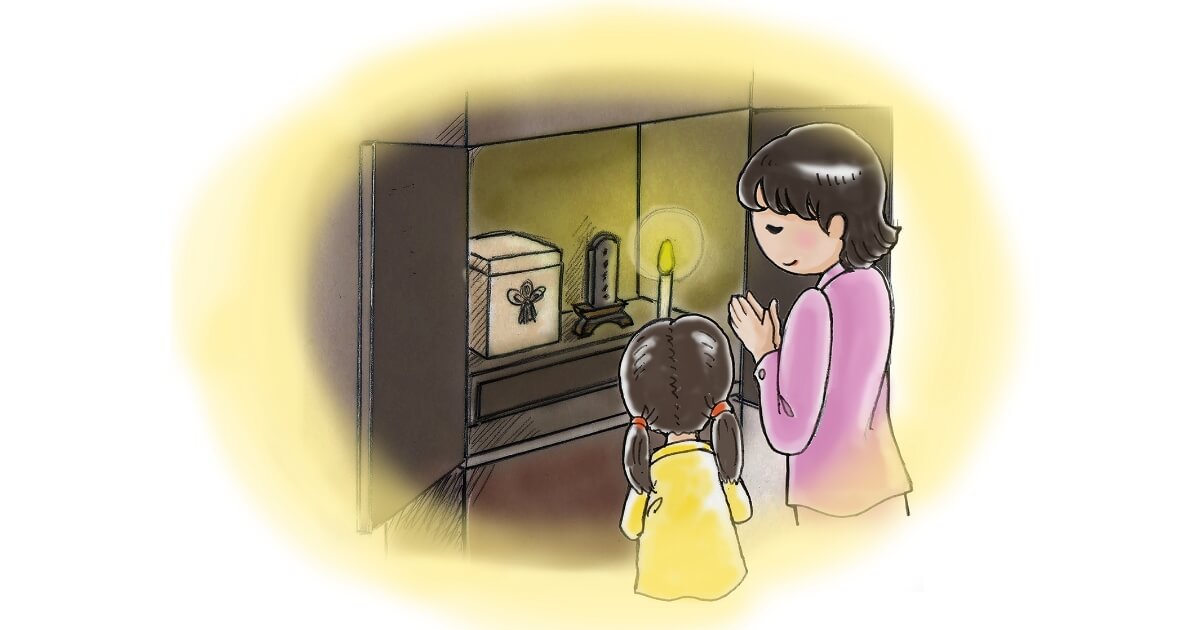
近年、東京都内で総面積900坪以上の納骨堂が建設され話題になりました。このように近代的な納骨堂が年々増えています。
納骨堂が増えている理由としては少子高齢化が関係しています。後継者が不足し、お墓を守る人がいなくなりつつあるのが現状です。無縁墓になる前に、管理が容易な納骨堂を選択する人が多く見られます。
また、ほとんどの納骨堂はアクセスが便利な場所にあります。高齢者にとって遠い場所への墓参りは一苦労です。通いやすいという理由で自宅に近い納骨堂に切り替える人が増えています。
日本は土地が狭い上に、法律により新規の墓地建設は制約を受けます。納骨堂は狭い土地でも多くの遺骨を管理できることから、国内で納骨堂の建設が急増しています。
納骨堂の費用相場
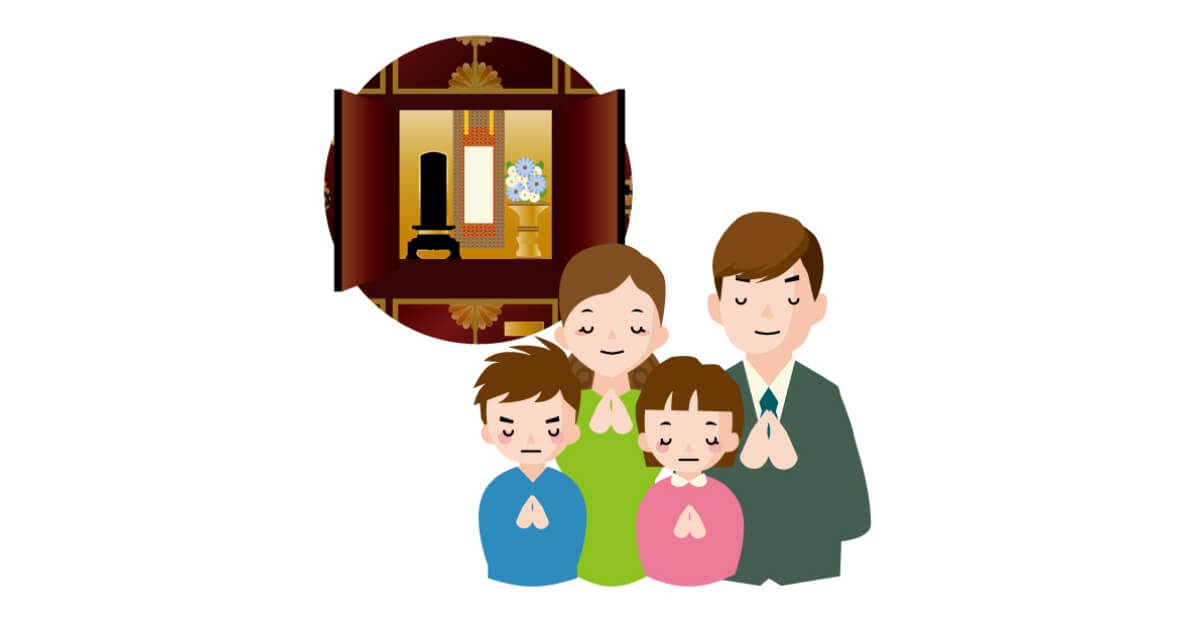
納骨堂の費用相場は、納骨の方式・年数・運営によって変化します。かかる費用のほとんどが遺骨を管理してもらう永代供養料です。それ以外に管理費として年間約1万円を要求されることもあります。
種類別に相場を見ていくと、
- 「ロッカー型」の費用相場
20万円~80万円です。ロッカーが上の位置だと価格が高くなる場合もあります。 - 「仏壇型」・「墓石型」の費用相場
平均して100万円前後です。それとは別に仏像代・墓石代がかかる場合もあります。
利用できる年数は3年、13年、33年のなかから選択することが多いです。アクセスのよい都心の納骨堂は相場が高く、公営の納骨堂は安く済みます。メリット・デメリットをよく勘案して、身の丈にあった納骨堂を選ぶようにしましょう。
納骨堂のメリット・デメリット
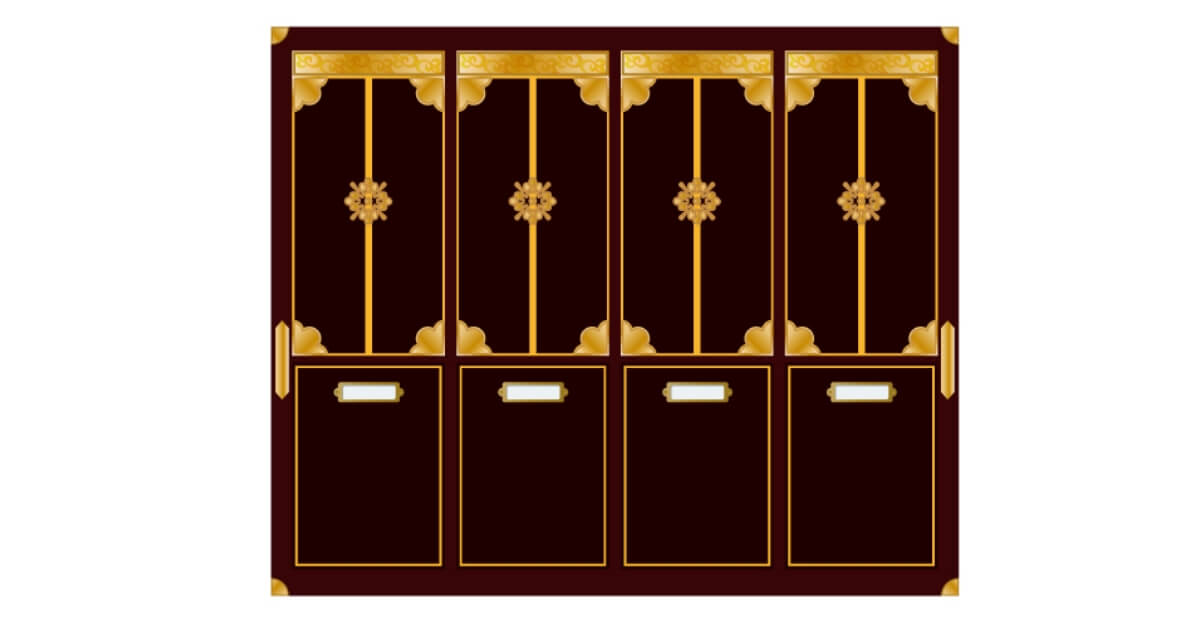
納骨堂のメリットはお墓と比べて管理費が安く済むことです。アクセスのよい納骨堂であれば、天候を気にせず気軽に礼拝に赴くことも可能です。
また、面倒な墓掃除も必要としないため、他に納骨堂に向いている人としては、後継者がいないため自分の代で墓を閉じようと考えている人が挙げられます。
デメリットとして、納骨堂は利用期間が決まっていることです。利用期間が過ぎた後には合祀墓に他の遺骨と一緒に納められます。納骨堂も建物である以上老朽化は避けられず、改築・移転の際に遺骨がどうなるかわからないという面もあります。
また、納骨堂は限られた空間に大量の遺骨が納められているため、ゆっくりと礼拝するには不向きでもあります。
まとめ
今回は、納骨堂の特徴や種類、費用相場やメリット・デメリットについてお伝えしました。
近年のライフスタイルの変化により、従来のお墓ではなく納骨堂に遺骨を収蔵する人が増えており、納骨堂の利用を検討している人も多いかと思います。
納骨堂は費用が安く立地等についても便利な反面、従来のお墓にはないデメリットなども存在します。メリット・デメリットを踏まえたうえで、ご家族と相談して決めるようにしましょう。


.jpg)

.jpg)









