お墓参りは懐かしいご先祖様と再会できる大切な時間。とはいえ、たびたび訪れることができないだけに、どうしても気になってしまうのが墓石についた汚れです。
特に石に生えたコケやカビは、しっかりこびりついて落ちにくく厄介なものですが、コツさえ押さえればわりと簡単に落とすことができます。
そこで今回は、次のお墓参りで早速お試しいただけるように、墓石に生えたコケ汚れをきれいにお掃除する方法についてポイントをご紹介します。
なぜ墓石にコケ(苔)が生えるのか
そもそも、墓石のような硬いものになぜコケが生えるのでしょうか。
植物が成長するときは、根を伸ばしてそこから水や養分を取り入れて大きくなるものですが、コケの成長の仕方は少し違います。
じつはコケには根がなく、通常は胞子として空中をさまよっており、風に乗って落ちたところで生育します。
根がないことから育つ環境は土の上である必要はなく、ほんの少しの日の光と水と養分があれば、石やコンクリートの表面であっても張り付いて生きていくことができるため、墓石でもコケが生えてしまうのです。
墓石のコケは落として良い?
お墓という神聖な場所に生えているコケを普通の汚れのように落としてしまってもいいのだろうか、と迷う気持ちがあるかもしれません。
しかし、墓石にコケが生えるのは自然の摂理で、汚れをきれいにするのはまったく心配する必要のないことです。
また、「掃苔(そうたい)」という言葉は墓のコケをきれいに掃き清めることをいいますが、これは墓参りのことを表す言葉でもあります。
秋の季語にもなっており、昔から墓参りに墓石のコケを掃除していたことがよくわかります。
墓石のコケ掃除に必要な掃除道具
墓石のコケは石に根を生やしているわけではなく、張り付いているだけであるため、こそげ落とすことを基本に、主に次のような道具を使って掃除していきます。
軍手
墓石の表面の落としやすいコケをそぎ落とすときは、軍手をはめて手で落とします。軍手は2枚重ねにした方が手が汚れにくく、また力も入りやすいです。
スポンジ・たわし
墓石全体の汚れをきれいにするときに使います。頑固な汚れはたわしを使って落とします。
歯ブラシ・台所用ブラシ
墓石に刻まれた文字の奥に生えたコケ落としに使います。歯ブラシで届かないときは毛足の長い台所用ブラシが便利です。台所用ブラシは花立の奥のコケを落とすのにも使いますので、なるべく柄の長いものを用意します。
石材用洗剤
水洗いで落ちない汚れがある場合は、洗剤を使用します。墓石を傷つけないよう石材用の洗剤を選ぶことが必要です。
タオル・雑巾
仕上げのふき掃除のために乾いたタオルか雑巾を用意します。
墓石のコケを落とす掃除方法と手順
①水を流す
墓石のコケを落とす前にまず全体に水を流してほこりを落とします。
②コケを落とす
次に軍手をはめた手で、墓石に生えたコケをこそげ落としていきます。墓石の文字の奥のコケは歯ブラシを使ってこすり落としますが、歯ブラシの毛先が届かないときは毛先の長い台所用ブラシを使います。花立や線香立て等もブラシ類で掃除します。
③スポンジでこする
この段階でほぼコケは落ちていますので、仕上げに水を含ませたスポンジで残った汚れを掻き出していきます。スポンジで落としきれない頑固な汚れはたわしを使ってこすり落とすことも方法の一つですが、あまりゴシゴシこすりすぎて墓石を傷めないように注意が必要です。
④しつこい汚れは石材用の洗剤を使用する
それでも落ちない汚れがある場合は、石材用の洗剤を使用します。例えば、台所用の中性洗剤では墓石にシミをつけてしまう恐れもありますので、必ず石材用の洗剤を使うようにしましょう。
⑤しっかり水で洗い流す
洗剤を使った場合はしっかり水で洗い落して、全体を再度スポンジで水洗いします。
⑥乾いたタオルで水分を拭き取る
最後に乾いたタオルや雑巾で水分を拭き取ります。このとき水分のふき残しなどがあるとコケやカビが生えやすくなってしまいますので、しっかりとふき取ることが大切です。
まとめ
墓石のコケは見た目には頑固にこびりついているようでも、掃除のポイントを押さえれば簡単に落とせるものです。
ただし、無理にこすりすぎて墓石を傷つけないこと、洗浄後は水をしっかりふき取ることといった点には十分な注意が必要です。
お墓は大切なご先祖様が眠る場所ですから、いつも晴れやかな気持ちでお参りができるよう、お墓参りをするたびにきれいにお掃除をしておきましょう。


.jpg)
.jpg)



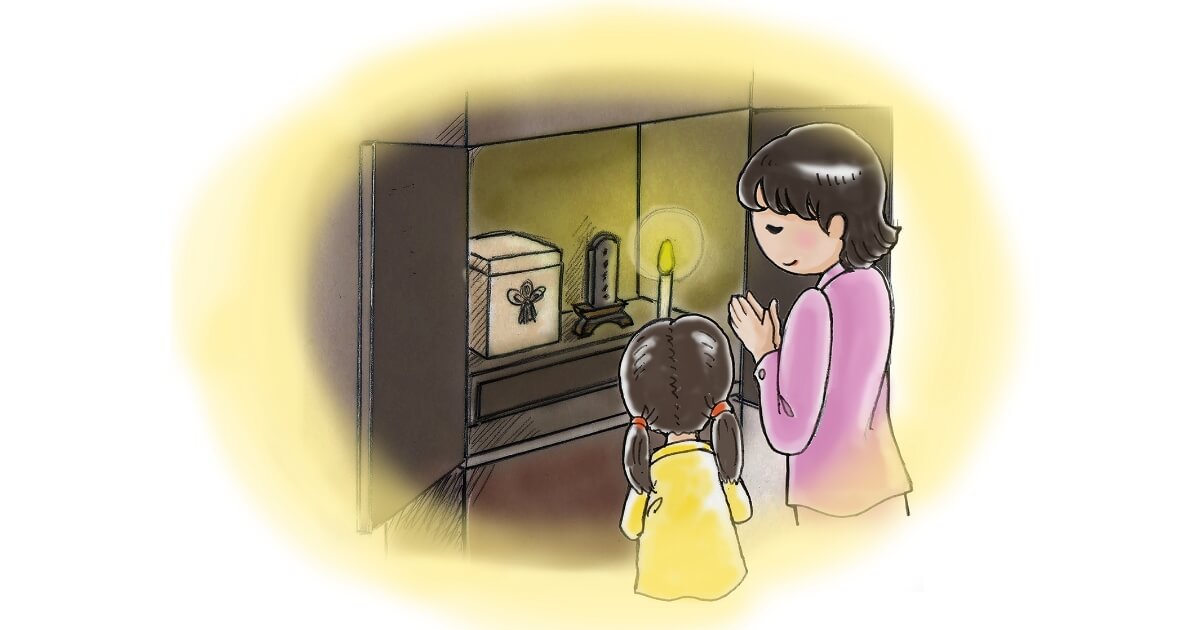
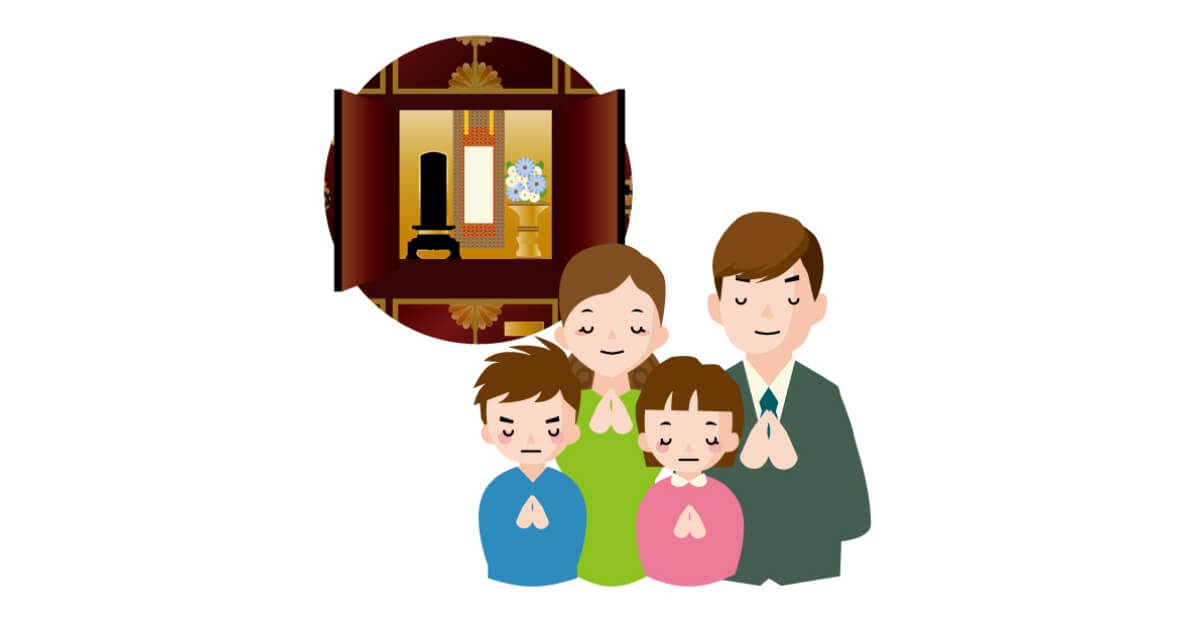
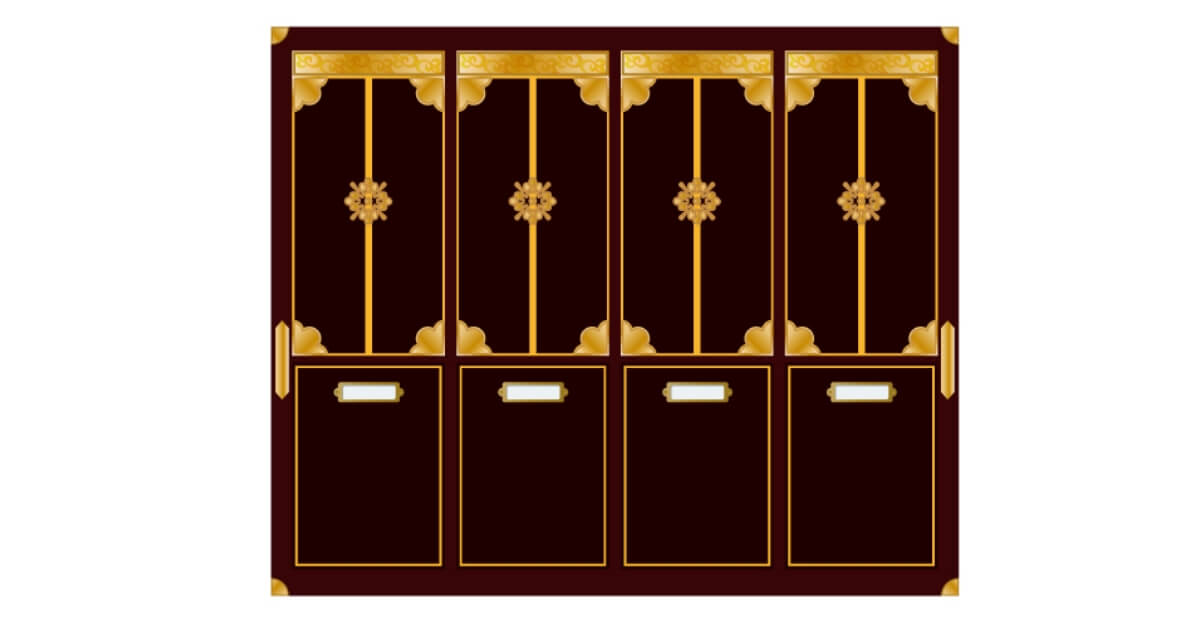
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)



















